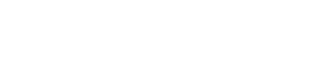Chapter 8 Vol.One
EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
Tomoki Koharu
小春友樹
江戸和竿は江戸の庶民文化として発展し、現在では東京都の伝統工芸品のひとつに指定されている。「小江戸」と呼ばれる埼玉県川越市に、江戸和竿の伝統を受け継ぐ若き職人がいる。川越を拠点とする小春友樹だ。彼の工房があるのは、川越の旧市街に建つ築120年の長屋「喜多町弁天長屋」。この長屋を舞台とする、ものづくりと町の再生にまつわるストーリーを文筆家の大石始が綴る。
埼玉県南西部に位置する川越市は、35万の人口を抱える埼玉第三の都市だ。江戸時代から川越藩の城下町として栄え、かつては「世に小京都は数あれど、小江戸は川越ばかりなり」とも謳われた。戦後、各地の農村が都市部で働く労働人口の受け皿として宅地化されていったが、川越もまた戦後になってから町としての規模を大きく拡張させた郊外地域のひとつであった。

川越は伝統が息づく町でもある。旧市街地ではレトロな蔵造りの町並みが保存されており、近年は観光地としても人気を集めている。週末ともなると着物姿で着飾ったカップルが街歩きを楽しみ、一部の飲食店には長蛇の列ができる。市制施行100周年となる2022年にはさまざまなメディアで川越の歴史と名所が取り上げられた。
そんな旧市街地の一角に、川越のアートとものづくりの発信拠点がある。それが2021年にオープンした「喜多町弁天長屋」だ。かつては芸者の置き屋だったという築120年の長屋をリノベーションしたこのスペースは、川越の新たな顔ともいえる場所である。川越を舞台とする今回のストーリーでは、この長屋の一室を工房とする江戸和竿の職人、小春友樹さんを主人公としながら、街で育まれる新たなものづくりのあり方について掘り下げていく。
 ちなみに、この記事にはサイドストーリーが存在する。それは筆者である僕自身が川越で育ちながら、この街に対してアンビバレントな感情を抱えてきたということだ。僕が育ったのは川越でも観光客が行き交う旧市街ではなく、トラックが黒煙を上げながら走る国道16号線近くの地域。現在では家族全員が都内で生活しており、僕も含めて川越との縁はほぼ切れている。
ちなみに、この記事にはサイドストーリーが存在する。それは筆者である僕自身が川越で育ちながら、この街に対してアンビバレントな感情を抱えてきたということだ。僕が育ったのは川越でも観光客が行き交う旧市街ではなく、トラックが黒煙を上げながら走る国道16号線近くの地域。現在では家族全員が都内で生活しており、僕も含めて川越との縁はほぼ切れている。
僕にとっての川越とは、決して「故郷」や「地元」といえるような場所ではなかった。あくまでも幼少時代の一時期を過ごした土地に過ぎず、愛着もほとんどない。むしろ後足で砂をかけるようにして出てきたこともあって、川越に対してモヤモヤしたものさえ抱えてきた。だが、僕は小春さんと弁天長屋の人々を通じ、幼少時代を過ごした川越という街と出会い直していくことになるのだ。
そんな旧市街地の一角に、川越のアートとものづくりの発信拠点がある。それが2021年にオープンした「喜多町弁天長屋」だ。かつては芸者の置き屋だったという築120年の長屋をリノベーションしたこのスペースは、川越の新たな顔ともいえる場所である。川越を舞台とする今回のストーリーでは、この長屋の一室を工房とする江戸和竿の職人、小春友樹さんを主人公としながら、街で育まれる新たなものづくりのあり方について掘り下げていく。

僕にとっての川越とは、決して「故郷」や「地元」といえるような場所ではなかった。あくまでも幼少時代の一時期を過ごした土地に過ぎず、愛着もほとんどない。むしろ後足で砂をかけるようにして出てきたこともあって、川越に対してモヤモヤしたものさえ抱えてきた。だが、僕は小春さんと弁天長屋の人々を通じ、幼少時代を過ごした川越という街と出会い直していくことになるのだ。

2022年10月、僕は関越自動車道を北上して川越へと車を走らせていた。練馬インターチェンジから高速道路に乗ってしまうと、わずか20分足らずで川越に到着。もう少し走っていたくなるぐらいの近さだ。
目的地である喜多町弁天長屋は、蔵造りの商店・家屋が立ち並ぶ一番街商店街を少し入ったところにある。一番街を訪れるのはひさしぶりのことだったが、その賑わいに僕は驚いてしまった。平日だというのに多くの観光客が行き交い、どの店も大繁盛。一番街は重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、電柱を地中に埋め込む無電柱化が実施されている。そのため空が広々としていて街歩きもしやすそうだ。
僕からしてみると、そうした一番街の光景は衝撃的なものだった。なぜならば僕が子供のころ、このあたりは薄暗くて活気がなく、不用意に歩いているとヤンキーに絡まれてカツアゲされかねない雰囲気があったからだ。パンチパーマの男がシンナーの入ったビニール袋を片手に白いセダンを運転している姿を見かけたのもこのあたりだったし、中学生のころ、ガラの悪い男たちに絡まれたこともあった。だが、現在の一番街にそんな雰囲気は微塵もない。
目的地である喜多町弁天長屋は、蔵造りの商店・家屋が立ち並ぶ一番街商店街を少し入ったところにある。一番街を訪れるのはひさしぶりのことだったが、その賑わいに僕は驚いてしまった。平日だというのに多くの観光客が行き交い、どの店も大繁盛。一番街は重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、電柱を地中に埋め込む無電柱化が実施されている。そのため空が広々としていて街歩きもしやすそうだ。
僕からしてみると、そうした一番街の光景は衝撃的なものだった。なぜならば僕が子供のころ、このあたりは薄暗くて活気がなく、不用意に歩いているとヤンキーに絡まれてカツアゲされかねない雰囲気があったからだ。パンチパーマの男がシンナーの入ったビニール袋を片手に白いセダンを運転している姿を見かけたのもこのあたりだったし、中学生のころ、ガラの悪い男たちに絡まれたこともあった。だが、現在の一番街にそんな雰囲気は微塵もない。

マップを頼りに喜多町弁天長屋をめざして歩いていくと、古びた看板が目に入った。クラブ浮世、ロートレック、小料理 悦、パプ河。この通りはかつて弁天横丁と呼ばれ、スナックや飲食店が立ち並んでいたというが、看板はその名残りを伝えるものである。どの店も現在は営業していないが、ひとたび足を踏み入れてみて、幼少時代に自転車でこの通りに迷い込んだことがあったことを思い出した。今にも崩れ落ちそうな廃屋も点在するその通りは、幼かった僕には明らかに場違いな場所だった。子供ながらに良からぬものを感じ、立ち漕ぎで走り抜けたことを覚えている。それからおよそ40年ぶりの再訪である。
喜多町弁天長屋に向かっていると、小春さんが僕を出迎えてくれていた。僕と小春さんは10年ほど前に音楽の場で出会ったが、そのときの彼はジャマイカンミュージックをかけるDJだったはずだ。当時長かった髪はすっかり短くなっていて、今ではDJの雰囲気はほとんどない。江戸和竿の職人になったというからてっきり仙人のような風貌を想像していたけれど、そこまでの変貌ぶりではない。とはいえ数年ぶりの再会だったこともあり、数年分の歳月の経過がその佇まいにはっきりと現れていた。
「小春さん、お久しぶりです」
「お久しぶりです、何年ぶりですかね?」
優しいその口調は以前と変わらなかった。いくらかほっとすると、早速長屋を案内してもらうことになった。
喜多町弁天長屋に向かっていると、小春さんが僕を出迎えてくれていた。僕と小春さんは10年ほど前に音楽の場で出会ったが、そのときの彼はジャマイカンミュージックをかけるDJだったはずだ。当時長かった髪はすっかり短くなっていて、今ではDJの雰囲気はほとんどない。江戸和竿の職人になったというからてっきり仙人のような風貌を想像していたけれど、そこまでの変貌ぶりではない。とはいえ数年ぶりの再会だったこともあり、数年分の歳月の経過がその佇まいにはっきりと現れていた。
「小春さん、お久しぶりです」
「お久しぶりです、何年ぶりですかね?」
優しいその口調は以前と変わらなかった。いくらかほっとすると、早速長屋を案内してもらうことになった。

長屋にはさまざまな人々が入居している。鉄工房のオリジナルプロダクトを販売している「bero弁天長屋」。「THE SUN」という屋号でデザイン関係の仕事をしている安田太陽さん。アトリエ兼ギャラリーの「Caoli Art Studio」。着物の着付け教室である「キモノ・キツケ ハナノワ」。人力車の事務所である「いつき屋」。ハンドメイドサインの製作を行う「REMODULE PAINTING」。同じ横丁に建つ麻利弁天長屋のギャラリー「なんとうり」の分室。地域住民との交流も目的とする「トモリ食堂」。いずれも個性溢れる入居者ばかりだ。
小春さんの工房は長屋の離れにある。小春さんによると「おそらく従業員の休憩室だったと思います」とのこと。この長屋が芸者の置き屋だったのは戦後まもない時期までで、それ以降は「悦」という名の小料理として営業していたらしい。こちらも決して広いスペースではないけれど、小春さんの手の届く範囲にあらゆる道具が揃っていて、使い勝手は良さそうだ。
小春さんの工房は長屋の離れにある。小春さんによると「おそらく従業員の休憩室だったと思います」とのこと。この長屋が芸者の置き屋だったのは戦後まもない時期までで、それ以降は「悦」という名の小料理として営業していたらしい。こちらも決して広いスペースではないけれど、小春さんの手の届く範囲にあらゆる道具が揃っていて、使い勝手は良さそうだ。

長屋の歴史に触れる前に、まずは小春さん自身の半生について話を伺おう。いざ取材をするとなって気づいたことだが、そういえば彼がこれまでどんな人生を歩んできたのかほとんど知らないのだ。
「僕自身の生まれは練馬区の上石神井なんです。でも、生まれてすぐにこっちに来たので、育ちは川越ですね」
「ご両親は川越に縁があったんですか?」
「いや、ないですね。父は(東京の)中野で、母は東北出身です」
小春さんと僕には共通点が多かった。年齢はほぼ同世代。両親とも川越出身ではなく、血縁や地縁があったわけでもない。都心で働く父親のことを考慮し、都心から埼玉へと伸びる東武東上線沿線沿いにマイホームを購入した(しかも僕らの父親は偶然にも同じ系列の会社で働いていたことが判明した)。両親は団塊世代、その子供である僕らは団塊ジュニア世代。ただし、こうした家族構成は決して珍しいものではない。池袋から伸びる東武東上線沿線や西武池袋線・新宿線沿いには、僕らのように団塊世代と団塊ジュニアで構成される(いわゆる)ニューファミリーが大量に住んでいたのだ。
僕が育った地域が国道16号線近くだと伝えると、小春さんの地元とも近いことがわかった。驚くことに、通っていた釣り堀まで一緒。当時は漫画『釣りキチ三平』の影響で爆発的な釣りブームが巻き起こっていたが、小春さんも僕と同じように伊佐沼や入間川といった近隣の釣りスポットへと出かけていた。そう考えると、小学生のころ、僕らは隣り合って釣り糸を垂らしていた可能性もあるわけだ。
ただし、小春さんと僕が大きく違う点がある。小春さんは子供のころからものづくりが好きで、ルアーやウキを自作していたのだ。
「ただ、手先は決して器用じゃないんですよ。プラモデルも完成させたことがなかったぐらいで。ただ、『釣りキチ三平』の影響で子供のころから竿師に憧れていました。(『釣りキチ三平』の登場人物である)一平じいさんは竿師なんですよね。『釣りキチ三平』には『小さなビッグゲーム』っていうタナゴ釣りの話があるんですけど、その内容も鮮明に覚えています」
さすが将来の竿師。当時星の数ほどいた釣り好き小学生のなかでも、小春さんは釣りに対して頭ひとつ抜けた熱意を持っていたようだ。
とはいえ、小春さんは成人後すぐさま江戸和竿の道に突き進んだわけではなかった。現在の彼からは想像できないけれど、そのころの小春さんは女性向けのアパレルメーカーで営業の仕事をしていたという。
「ラフォーレ原宿が全盛のころ、メーカーで営業の仕事をやっていました。アパレルって昔の体育会系のノリがあって、どうも合わなくて。満員電車に乗るのも苦痛だったし、身体を壊しちゃいましたね」
心身ともにボロボロになった小春さんは、およそ10年もの闘病生活を送ることになる。人生に悩み、先の見えない日々を送る小春さんにとって、釣り場は数少ない心休まる場所だった。小春さんはそんなとき、江戸和竿に出会うのである。
「びん沼川(埼玉県富士見市)で釣りをしていたら、和竿でタナゴ釣りをしている人がいたんですよ。これ(和竿)を作ってるのはどんな人なんだろう? と思って調べてみたら、川越にもいるらしい。ただ、和竿を売ってるところで聞いてみても、どこで作ってるのか教えてくれないんですね。釣り場で聞いてまわったら、和竿を作ってる人がたまにくることがわかって。そのころ無職で暇だったんで、半年ぐらい釣り場に通い続けたんです。そこに親方がやってきたんですよ」
それが小春さんにとって最初の師匠となる寿代作親方だった。
「親方はちょうどおかみさんを亡くしたばかりで。80代でひとり暮らしだし、『竿作りに興味があるんです』という話をしたら『遊びに来ていいよ』と。運がよかったんです」
そして、江戸和竿の職人となるための試練の日々が始まることになる。
「僕自身の生まれは練馬区の上石神井なんです。でも、生まれてすぐにこっちに来たので、育ちは川越ですね」
「ご両親は川越に縁があったんですか?」
「いや、ないですね。父は(東京の)中野で、母は東北出身です」
小春さんと僕には共通点が多かった。年齢はほぼ同世代。両親とも川越出身ではなく、血縁や地縁があったわけでもない。都心で働く父親のことを考慮し、都心から埼玉へと伸びる東武東上線沿線沿いにマイホームを購入した(しかも僕らの父親は偶然にも同じ系列の会社で働いていたことが判明した)。両親は団塊世代、その子供である僕らは団塊ジュニア世代。ただし、こうした家族構成は決して珍しいものではない。池袋から伸びる東武東上線沿線や西武池袋線・新宿線沿いには、僕らのように団塊世代と団塊ジュニアで構成される(いわゆる)ニューファミリーが大量に住んでいたのだ。
僕が育った地域が国道16号線近くだと伝えると、小春さんの地元とも近いことがわかった。驚くことに、通っていた釣り堀まで一緒。当時は漫画『釣りキチ三平』の影響で爆発的な釣りブームが巻き起こっていたが、小春さんも僕と同じように伊佐沼や入間川といった近隣の釣りスポットへと出かけていた。そう考えると、小学生のころ、僕らは隣り合って釣り糸を垂らしていた可能性もあるわけだ。
ただし、小春さんと僕が大きく違う点がある。小春さんは子供のころからものづくりが好きで、ルアーやウキを自作していたのだ。
「ただ、手先は決して器用じゃないんですよ。プラモデルも完成させたことがなかったぐらいで。ただ、『釣りキチ三平』の影響で子供のころから竿師に憧れていました。(『釣りキチ三平』の登場人物である)一平じいさんは竿師なんですよね。『釣りキチ三平』には『小さなビッグゲーム』っていうタナゴ釣りの話があるんですけど、その内容も鮮明に覚えています」
さすが将来の竿師。当時星の数ほどいた釣り好き小学生のなかでも、小春さんは釣りに対して頭ひとつ抜けた熱意を持っていたようだ。
とはいえ、小春さんは成人後すぐさま江戸和竿の道に突き進んだわけではなかった。現在の彼からは想像できないけれど、そのころの小春さんは女性向けのアパレルメーカーで営業の仕事をしていたという。
「ラフォーレ原宿が全盛のころ、メーカーで営業の仕事をやっていました。アパレルって昔の体育会系のノリがあって、どうも合わなくて。満員電車に乗るのも苦痛だったし、身体を壊しちゃいましたね」
心身ともにボロボロになった小春さんは、およそ10年もの闘病生活を送ることになる。人生に悩み、先の見えない日々を送る小春さんにとって、釣り場は数少ない心休まる場所だった。小春さんはそんなとき、江戸和竿に出会うのである。
「びん沼川(埼玉県富士見市)で釣りをしていたら、和竿でタナゴ釣りをしている人がいたんですよ。これ(和竿)を作ってるのはどんな人なんだろう? と思って調べてみたら、川越にもいるらしい。ただ、和竿を売ってるところで聞いてみても、どこで作ってるのか教えてくれないんですね。釣り場で聞いてまわったら、和竿を作ってる人がたまにくることがわかって。そのころ無職で暇だったんで、半年ぐらい釣り場に通い続けたんです。そこに親方がやってきたんですよ」
それが小春さんにとって最初の師匠となる寿代作親方だった。
「親方はちょうどおかみさんを亡くしたばかりで。80代でひとり暮らしだし、『竿作りに興味があるんです』という話をしたら『遊びに来ていいよ』と。運がよかったんです」
そして、江戸和竿の職人となるための試練の日々が始まることになる。

ここで江戸和竿の文化について小春さんに解説していただこう。
「和竿は紀州や庄内とか各地方にあって、江戸和竿は江戸で発展した地方竿ということですよね。特徴としては魚種によって竿が異なるということ。マブナ、タナゴ、ワカサギ、海で釣れるハゼやスズキ、タイ、コチ。それぞれの魚専用の竿があるんですよ。それと、小継ぎといって竿自体が細かく分かれていること、装飾が凝っていることも特徴です。漆塗りをふんだんに使っていたり、部屋に置いてあっても目を楽しませてくれるんです」
「なぜ魚種によって竿が違うんですか?」
「江戸だけなんですよ、そこらへんの小魚から海の大物まで竿の種類があるのは。京都の京竿もアユとヤマメぐらいですからね。江戸の釣り文化の豊かさもあったのかもしれない」
そう話す小春さんが現在作っているのはマブナ用の竿。コイを釣るような太い竿を見慣れていると、これでも十分細いが、タナゴ用ともなるとまるで爪楊枝のようだ。バラすと小さなケースに収まってしまうほどのサイズで、なんとも愛らしい。 小春さんによると、和竿と大量生産の太竿では釣り上げたときの感触も違うのだという。
小春さんによると、和竿と大量生産の太竿では釣り上げたときの感触も違うのだという。
「竹はアタリがダイレクトに伝わってくるんですよ。量を釣るのであれば最新の竿のほうがいいと思うんですけど、和竿には独特の釣り味があって、好きな人は好きですね。あとは持っていて所有欲が満たされる。自分のオーダー通りに作ってもらうという喜びがあるんです」
確かに目の前に並べてもらった和竿には工芸品としての美しさと気品がある。江戸時代末期には和竿に関する多くの技術が完成していたそうで、小春さんは「当時の名人が作ったものを見ると本当にすごいんですよ。もう完成形。道具がないその時代にここまでできるなんて、どういうことなんだろう? と思いますね」とも話す。
「江戸和竿」の源流は天明年間(1781~1788年)、上野広徳寺前に開業した泰地屋東作(通称「東作」)にあるとされている。江戸時代末期には二代目東作のもとで修業した釣音こと中根音吉が活躍。釣音の長男である竿忠こと中根忠吉(1864~1930年)が江戸和竿の名作を数多く生み出し、この時期が江戸和竿の全盛期とされている。戦後はグラスファイバーなど耐久性に優れた竿が一般化し、竹を使った和竿は急激に衰退する。そのため、下町を拠点としていた職人たちは千葉や川口など東京の近郊に流れていったという。
川越には決して多くの職人がいたわけではなかったが、小春さんが最初に師事した寿代作親方は川越を拠点とする職人のひとりだった。
「早く竿師になりたくて焦っていたので、親方のところに毎日通ってたんですけど、毎日ともなると親方も疲れるんでしょうね。お前が来ると釣りにいけないから、他にいないのか? と言われるようになって。竿師ってほとんど食えないので、名人も自分の息子にはまず継がせないんですよ。それぐらいの状況なので、親方は『責任を取れない』って言ってました。だから、『他のところに行きなよ』と言いながら、『食えないからやめなよ』ということでもあったと思うんですね。でも、諦めなかったんです」
「和竿は紀州や庄内とか各地方にあって、江戸和竿は江戸で発展した地方竿ということですよね。特徴としては魚種によって竿が異なるということ。マブナ、タナゴ、ワカサギ、海で釣れるハゼやスズキ、タイ、コチ。それぞれの魚専用の竿があるんですよ。それと、小継ぎといって竿自体が細かく分かれていること、装飾が凝っていることも特徴です。漆塗りをふんだんに使っていたり、部屋に置いてあっても目を楽しませてくれるんです」
「なぜ魚種によって竿が違うんですか?」
「江戸だけなんですよ、そこらへんの小魚から海の大物まで竿の種類があるのは。京都の京竿もアユとヤマメぐらいですからね。江戸の釣り文化の豊かさもあったのかもしれない」
そう話す小春さんが現在作っているのはマブナ用の竿。コイを釣るような太い竿を見慣れていると、これでも十分細いが、タナゴ用ともなるとまるで爪楊枝のようだ。バラすと小さなケースに収まってしまうほどのサイズで、なんとも愛らしい。

「竹はアタリがダイレクトに伝わってくるんですよ。量を釣るのであれば最新の竿のほうがいいと思うんですけど、和竿には独特の釣り味があって、好きな人は好きですね。あとは持っていて所有欲が満たされる。自分のオーダー通りに作ってもらうという喜びがあるんです」
確かに目の前に並べてもらった和竿には工芸品としての美しさと気品がある。江戸時代末期には和竿に関する多くの技術が完成していたそうで、小春さんは「当時の名人が作ったものを見ると本当にすごいんですよ。もう完成形。道具がないその時代にここまでできるなんて、どういうことなんだろう? と思いますね」とも話す。
「江戸和竿」の源流は天明年間(1781~1788年)、上野広徳寺前に開業した泰地屋東作(通称「東作」)にあるとされている。江戸時代末期には二代目東作のもとで修業した釣音こと中根音吉が活躍。釣音の長男である竿忠こと中根忠吉(1864~1930年)が江戸和竿の名作を数多く生み出し、この時期が江戸和竿の全盛期とされている。戦後はグラスファイバーなど耐久性に優れた竿が一般化し、竹を使った和竿は急激に衰退する。そのため、下町を拠点としていた職人たちは千葉や川口など東京の近郊に流れていったという。
川越には決して多くの職人がいたわけではなかったが、小春さんが最初に師事した寿代作親方は川越を拠点とする職人のひとりだった。
「早く竿師になりたくて焦っていたので、親方のところに毎日通ってたんですけど、毎日ともなると親方も疲れるんでしょうね。お前が来ると釣りにいけないから、他にいないのか? と言われるようになって。竿師ってほとんど食えないので、名人も自分の息子にはまず継がせないんですよ。それぐらいの状況なので、親方は『責任を取れない』って言ってました。だから、『他のところに行きなよ』と言いながら、『食えないからやめなよ』ということでもあったと思うんですね。でも、諦めなかったんです」

「それはなぜ?」
「めちゃくちゃ魅力に感じたんですよ。これが仕事になったら幸せだろうなって。続ければどうにかなるだろうと思っていましたし」
寿代作親方のもとに通う日々は1年間に及んだ。満員電車に揺られ、ストレスを抱えながら仕事することに限界を感じていた小春さんは、ひたすら技術を磨き上げていく職人の世界に何か感じるものがあったのだろう。今後の人生をどのように生きていくか。思い悩んでいた小春さんにとって、それは人生の分岐点でもあった。
「最初は金が出ていくばかりなので、親も反対してたんですよ。でも、親方たちも楽しそうに和竿を作っているし、それこそ90代になっても手を動かしていた。それだけすごい仕事なんだなと思いましたし、めちゃくちゃやりがいを感じていました」
寿代作親方のもとに1年間通った小春さんは、のちに川越市内で活動する俊秀作親方のもとで2年間修行。その後独立し、「小春」という屋号で自身の竿を作り始める。それが8年前のことだ。そのとき小春さんは40代。自宅の一室を工房とし、江戸和竿の職人として新たな人生を歩み始めるのである。
「めちゃくちゃ魅力に感じたんですよ。これが仕事になったら幸せだろうなって。続ければどうにかなるだろうと思っていましたし」
寿代作親方のもとに通う日々は1年間に及んだ。満員電車に揺られ、ストレスを抱えながら仕事することに限界を感じていた小春さんは、ひたすら技術を磨き上げていく職人の世界に何か感じるものがあったのだろう。今後の人生をどのように生きていくか。思い悩んでいた小春さんにとって、それは人生の分岐点でもあった。
「最初は金が出ていくばかりなので、親も反対してたんですよ。でも、親方たちも楽しそうに和竿を作っているし、それこそ90代になっても手を動かしていた。それだけすごい仕事なんだなと思いましたし、めちゃくちゃやりがいを感じていました」
寿代作親方のもとに1年間通った小春さんは、のちに川越市内で活動する俊秀作親方のもとで2年間修行。その後独立し、「小春」という屋号で自身の竿を作り始める。それが8年前のことだ。そのとき小春さんは40代。自宅の一室を工房とし、江戸和竿の職人として新たな人生を歩み始めるのである。

小春友樹/江戸和竿師
1973年、東京生まれ。幼年期より埼玉県川越市在住。服飾メーカー営業職を経て、竿職人の道を目指す。川越市に工房を構える東作系江戸和竿師「寿代作」工房の門を叩き、1年間師事。その後、同市内の「俊秀作」の元へ2年間師事した後、独立。2020年より江戸和竿組合に加入。
-

FORESTER
Shigeaki Adachi
-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER
Kei Amano
-

BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER
Taiki Minakuchi
-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭 火付ぬ組
-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN
Yukihito Kanai
-

SAUNA BUILDER
nodaklaxonbebe