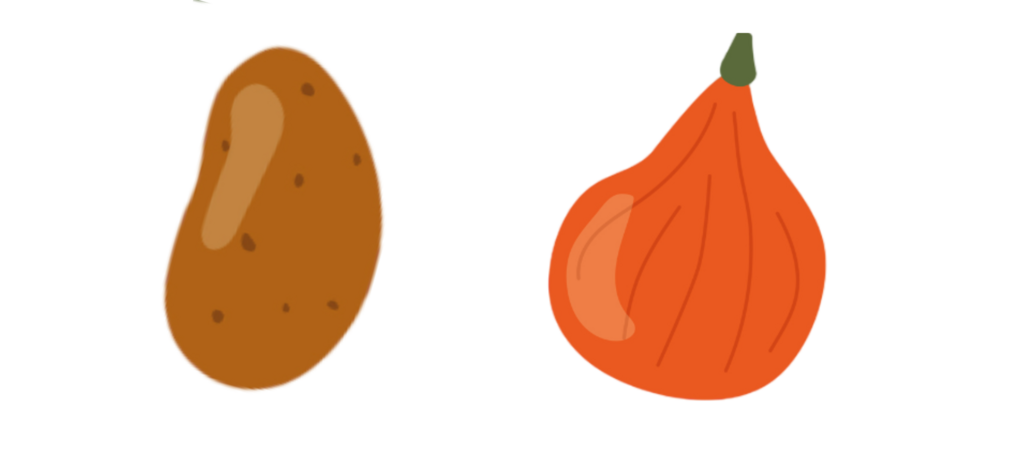その症状、夏の疲れからくる秋バテかも?
秋といえば「食欲の秋」「スポーツの秋」と楽しいことも多い季節。まだまだ暑さも残る中、特に朝夕は少しずつ過ごしやすい気候になっているはずなのに、「なんだか元気がないかも・・」「食欲がないかも・・」といった、身体の不調が気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。もしかしたら、それは暑い夏の疲れからくる秋バテも影響しているかもしれません。
ダンスキンアンバサダーでもありヨガインストラクターの村川美香さんが学ばれている、陰ヨガや中医養生ヨガには、生活に活かせる知恵がたくさん詰まっているそう。秋も健やかに前向きに過ごしていくための食養生、ヨガのポーズを教えていただきました。
中医学とは?
中医学とは2000年以上の歴史があり陰陽バランスの医学です。自然との調和と養生を提唱し、「喉が渇いてから井戸の水を掘るのではなく、喉が渇く前に掘っておく」予防を大切にする考えがあります。
中医学では前の季節の過ごし方が次の季節の身体に影響すると考えられています。もし秋バテのような不調を感じている場合、夏の過ごし方が影響しているかもしれません。これから深まる秋を健やかに過ごしていくためには、夏の疲れを回復させ、秋に身体を順応させていくことが大切です。
秋はどんな季節?
秋とは、立秋(8/7)から霜降(11/6)までの約3ヶ月を指します。秋は容平(ようへい)と呼ばれ、植物が実を結ぶように私たちも今まで積み重ねてきたことが「カタチ」となる季節です。
また、夏の疲れを回復させゆっくりと冬への準備をする季節でもあり、エネルギーを外に向け活動的に過ごす夏から、秋は少しずつ静かに冬に向けてエネルギーを蓄えながら落ち着いて過ごしていきましょう。
季節と心と身体のつながり

秋は五臓のうち【肺】とつながると考えます。【肺】は”喜潤悪燥”といって潤いを好んで乾燥を嫌う特徴があり、皮膚や鼻、大腸とも関わりがある臓器といわれています。自然界が乾燥してくることで、私たちも乾燥の影響を受けやすく、乾燥から身体を守り潤わせていくことが大切です。肺は肌の潤いや免疫力とも関係したり、正義感も肺気とつながるといわれます。反対に肺気が弱くなると呼吸器系の不調、皮膚の乾燥や、悲観的な感情、白黒はっきりつけたくなるといった気持ちになりやすいと言われています。
秋は陽が落ちるのが早くなり、落ち葉を見てはなんだかもの悲しい気持ちになりやすいかもしれませんね。ですが、季節と心と身体のつながりを知ることで自分を責めなくて良くなりますし、対策していくこともできます。全て大切な感情ですが、気持ちが沈みすぎてしまわないように、楽しいことをして気分転換したり、深呼吸もおすすめです。
これからご紹介する【肺】のケアもぜひ取り入れてみてくださいね。深まる秋に備え、夏の疲れを回復させ、乾燥から体を守り、季節と寄り添いながら過ごせるようなヒントをお伝えします。旬の食材で秋の身体を整える食養生
身体を整えるためにも大切な食事。ポイントは“旬をいただく”ことです。旬の食材は美味しく栄養が豊富で、その季節の身体を元気にしてくれます。
POINT
⚫︎元気を養う食材を取り入れる
⚫︎肺を潤すものを食べる
⚫︎ほんの少しの辛味を取り入れる
⚫︎食材に火を通して温かいものを食べる
⚫︎元気を養う食材を取り入れる
夏の暑さで消耗したエネルギーを回復させ、冬に向けて栄養を蓄えていくためにも、元気をつける食材がおすすめです。秋に美味しい、芋類、南瓜、きのこ類、お米、鮭、鯖、さんま、鶏肉など、こういった食材は気を補って身体を元気にしてくれます。
食べる時のポイントとして、気を補う食材には、気を巡らせる働きのあるネギ、大葉、玉ねぎ、柑橘類といった香りのいい食材と一緒に食べるのがおすすめです。
⚫︎肺を潤すものを食べる
乾燥してくる秋は、肺を潤すとされる「白い食材」をとるとよいといわれます。
大根、かぶ、長芋、レンコン、白ごま、豆腐、豆乳、豚肉、梨、りんご、白きくらげ、百合根、チーズ、蜂蜜などがあり、旬の食材が多いです。お粥は喉の渇きを潤してくれて、消化にもよく胃腸の疲れを感じている方にもおすすめです。体の外からの潤いケアだけでなく、食べ物で体の中からも潤いを補給しましょう。
⚫︎ほんの少しの辛味を取り入れる
秋になるとカレーを食べたくなったり、少しの辛味が欲しくなる季節です。辛味は体を温め、気の巡りをよくし、肺の働きを助けてくれる味。寒くなってくると巡りが滞りやすいため、辛味を上手に取り入れてみてください。とりすぎは肺を乾燥させてしまうので要注意です。(ネギ、生姜、胡椒、唐辛子、スパイスなど)
⚫︎食材に火を通して温かいものを食べる
夏は身体の熱を冷ますために、生野菜などを多く摂っていたかもしれません。これから冬に向けて寒さが増し体も冷えやすいので、体を冷やさないためにも、食材には火を通して温かい食事や飲み物を摂るようにしましょう。
秋にピッタリ!旬の食材を使ったレシピ3選

これからの時期にぴったりな「疲労回復しカラダを元気にする」、「胃腸を整える」、「カラダを潤す」旬の食材を使ったレシピを3つご紹介します。どれも簡単に手軽に作れるものばかりですので、秋の味覚を楽しみながら是非作ってみてくださいね。
【参鶏湯風スープ】
体力回復にオススメ!鶏肉は気を補い、身体も温めてくれます。塩麹でお肉もほろりと柔らかに。圧力鍋で10分!味付けはお塩だけで、美味しい参鶏湯が簡単にできます。※圧力鍋がない方はお鍋でも調理可能です

材料(4人分)
・手羽元 12本
・塩麹(お肉の10%)
・長ネギ 2本
・にんじん 1本
・生姜 スライス5枚
・にんにく 2かけ
作り方
1)手羽元はポリ袋に入れ、塩麹を馴染ませて30分ほどおく。
2)長ネギとにんじんは食べやすい大きさに切り、生姜はスライス、にんにくは丸ごと潰す。
3)圧力鍋に材料全てと、具材がかぶる程のお水を入れる。圧がかかったら弱火で10分加熱し、火を止め自然に圧が抜けるまで待つ。お好みでお塩で味を整える。
(※お鍋で作る場合は、40分〜1時間ほど煮込む)【鮭ときのこの炊き込みご飯】
体力回復し胃腸を整える!鮭は気と血を補い、体力の回復に。お腹を温め胃の調子もよくしてくれます。キノコ類も気を補ってくれて、特に干し椎茸は栄養価も高く、食欲がない時や元気をつけたい時におすすめです。

材料(4人分)
・お米 2合
・生鮭 2匹
・にんじん 適量
・干し椎茸 1つ
・お好みのきのこ 100グラム
・大葉or小葱 適量
・みりん 大さじ2
・醤油 大さじ2
・椎茸の戻し汁
作り方
※事前に干し椎茸を水につけて戻しておく
1)鮭はペーパーで水気をしっかり拭き取り、軽く塩を振っておく。にんじんは千切り、干し椎茸は薄切り、きのこも食べやすい大きさに切る
2)お米を洗い、調味料を入れ2合の目盛まで戻し汁を入れる。
3)キノコ、鮭の順に入れて炊飯する。
4)炊き上がったら鮭をほぐしながら混ぜる。器に盛り付け大葉やネギをトッピングする
※塩鮭を使う場合は醤油の量を調整してください【梨のコンポート】
梨や蜂蜜は肺を潤し、喉の痛みや、咳止めにおすすめです。効能が溶け出ている汁も捨てずに飲んでくださいね。※蜂蜜は1歳未満の乳児には使用を控えてください。その他の甘味料で代用可能です

材料
・梨 1個
・はちみつ 大さじ2
・水 200cc
・クコの実(あれば) 少量
作り方
梨を切ってすべての材料を鍋に入れ、柔らかくなるまで煮れば完成です。(20分くらい)秋におすすめの陰ヨガのポーズ
陰ヨガは、一つのポーズを2〜5分長いキープするのが特徴です。筋肉を脱力させ、関節、筋膜、靭帯、気血がめぐる【経絡】にも働きかけていきます。経絡とは気血の巡る通路のようなもので、経絡を通して、直接五臓六腑に働きかけていくことができるヨガとも言われています。
今回は腕の内側に流れる「肺」の経絡にアプローチした「オープンウィング」のポーズをご紹介致します。深い呼吸で肺の経絡に働きかけ、秋の肺を元気にしましょう。パソコンやスマートフォンで前屈みな姿勢になりがちな方にもおすすめです。ポーズの後の、呼吸の深まりや身体の感覚もぜひ味わってみてくださいね。
1 ) うつ伏せになり両手を広げ、左手を胸の内側につき身体を左側に開いていきます。

2) 脚の位置を安定させ、右腕の内側に7割くらいの心地よい刺激となるように調整し2〜3分ほどキープします。身体の力をぬいて、ゆったりした呼吸を繰り返します。
※肩の内側の骨が当たって痛みを感じる場合は、肩の下にタオルを挟んでみてください
※手は胸の横についたままでも、脚も安定する位置で問題ありません。ぜひご自身の身体に合わせて行ってみてください
3 ) ポーズをゆっくりとほどきポーズの後の余韻、呼吸の変化を感じてみましょう。反対側も同様に行います。

旬の食材や陰ヨガを取り入れながら、夏の疲れを回復させて、これから深まる秋も健やかに過ごしていきましょう。
※参考文献
「中医養生ヨガ®︎テキスト」 田中しのぶ 著